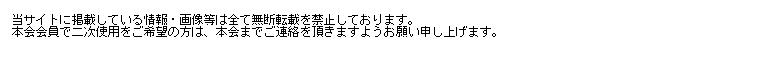2.学生時代の友人にリサーチ
秋田和也は大学のゼミが中島と同じで、下宿先も近所だったこともあり、学生時代からよく酒を酌み交わした。時には将来の夢をおおいに語り合った仲であり、今では家族ぐるみの付き合いもある。そんな間柄ゆえ、秋田にだけはつい現状の厳しさを愚痴ってしまう時がある。
秋田は総合商社の総和実業の貴金属販売部に所属している。職種は違えど、奇しくも扱う素材が中島と共通していることから、お互いに情報を交換する間柄でもある。
銀座の裏通りにある馴染みの小料理屋で乾杯したあと、お互いの近況を語り合うのはいつものこと。そして空腹が満たされ始めると、中島は今日の中心となる話題を切り出した。
「最近の貴金属価格の上昇はすごいな。何から何までって感じだ」
秋田は残ったビールを一気に流し込み、いつまでたっても治らない関西弁で答えた。
「ほんま、そうやな。俺も正直驚いてるんや。どんなに高くなっても次から次へと買いが入ってきよる」
中島は黙って聞いていた。
「まあ、それだけ世界中にお金が余ってるんやろ。そんな時に、今まで無かった商品ETF(上場投資信託)が世界中の証券取引所に上場したら、そら余ったお金で少しくらい買ってくるわな」
「そうだな」
「考えてもみろよ、そもそも市場の規模が違いすぎるんや。世界最大のコモディティ市場はニューヨーク原油市場やけど、その時価総額ってなんぼか知ってるか」
「いや、知らないな」
「約15兆円や。中国の外貨準備が約170兆円、世界最大の年金基金で約25兆円。他にも10兆円単位の年金基金なんて世界中探したらゴロゴロあるがな」
「そうだろうな」
「そいつらが資金のたった数パーセントを商品市場に振り分けただけで今のありさまや。しかも腰をすえて買いっぱなしときとる」
「買いっぱなしとはすごいな」
「そうや。仮に価格が急落しても、全資産に占める割合なんて微々たるもんや。痛くもかゆくもあれへん」
「なるほどな」
「そんなんやから、ファンドマネージャーから『商品への投資比率を引き上げる』なんて話がなんぼでも出てくるんや」
と秋田は浪花商人のごとくまくしたてた。
「そうか、そう考えると今後も高くなりそうだな。となると、プラチナもまだ上がるのか。我々の業界のプラチナジュエリーだけを見る限り、既に危機的なものがあるぞ」
「プラチナも、まだ上がるとしか言いようがないやろ。お前も知ってるやろが、自動車触媒需要の伸びの凄さを」
「ああ。以前から分かっていたこととはいえ、改めて秋田からも触媒需要といわれると、今ではプラチナは宝飾品ではなく、すっかり工業用貴金属になってきたと痛感せざるをえないな」
「そうや」
「プラチナ需要の半分以上が宝飾で、その8割以上を日本で消費していた時代がほんの数年前にあったなんて、全く嘘のようだ」
「中島よ、この傾向はますます強くなっていくぞ。欧州では環境と燃費効率の良さからディーゼル車が主流や。その流れが今、世界中に波及しつつあるんや」
「確か最近、ディーゼル車のベンツが販売されたな」
「そうや。今の中国なんかの成長が続く限り、車の売れ行きも伸びるやろ。たとえ1台では数グラムとわずかでも、今みたいに台数が売れたら必然的に量も増えていくからな」
中島も、残りのビールを一気に流し込み、呟いた。
「まあ、車両価格に占めるプラチナのパーセンテージなんて微々たるものだから、自動車メーカーにとっては吸収できる問題だろう。ただ、われわれ宝飾の場合は価格のうち素材価格が8割以上も占めるとなると正直、厳しいものがあるな」
秋田は黙って聞いていた。
「結婚指輪がプラチナなのは今も変わらないが、2000年のグラム1400円前後からわずか7年間で価格が5400円前後と約4倍だ」
「そら個人相手やと簡単に価格を上げられへんわな。競争も激しいやろうし」
「そうなんだ。だからリングなんかは年々細く薄くして、価格をなんとか据え置くしかないんだ」
「そうなるわな、現実問題。」
「それに、普段は使わないからという理由で婚約指輪を買わないカップルも増えているんだ。その分を新婚旅行や家具代に当てて、結婚指輪だけで済ますカップルも増えているんだな」
「たしかに、景気が良くなったとは言っても、実際に給料が増えたというのは大企業だけという話やしな。しかし、ここ最近のプラチナの上昇スピードは速いけど、だからといって長期的に下がる理由も見当たらへんねんな、これが」
「というと、触媒以外にも何か他の理由がありそうだな」
「そうなんや。プラチナ生産量の8割以上が南アフリカに偏在してるんは知ってるよな」
「ああ」
「その南アフリカの鉱山で事故が多いんや。まあ、価格の上昇で生産量を増やそうとした反動やな。昔はそうでもなっかたんやが、最近は事故のたびに原因究明と安全対策が徹底されて、鉱山閉鎖が相次いどんのやな」
「その他にも、鉱山会社に26%の黒人経営を参加させる法律や、新規鉱山ではなんと51%や。経営・開発のノウハウを持ってるんは主に白人やから、こうなると新規鉱山なんて開発できんやろ」
「そんな法律ができたのか」
「ああ、そうや。それに2010年にワールドカップがあるやろ。労働者も安全なインフラ整備の方に流れてるから、鉱山で働く人員確保も大変なんや。ストも増えてるしな。そんなんでも需要は増える一方や、でも供給は伸びへん。そうなったらどないなる」
「なるほど、それは深刻だな」
中島はヤレヤレという思いを持ちながらも、続く秋田の話に耳を傾けた。
「安定供給を望む自動車メーカーなんかは年間予算を組んで直接鉱山会社と長期契約するから問題ないとしても、その他のメーカーなんかは安いところを我々を通して、スポットで買ったりしてるからな。相対取引やから表に出ることはないんやけど、実際にはその分を東京工業品取引所の先物市場でヘッジすることもあるんや」
「メーカーの場合は、物がなくて作れません、ではお話にならないからな。納得だ」
「そらそうや、信用問題やからな」
「確実に需要が見込めるなら、安値で買える時に買っておこうという気持ちはわかるな。実はプラチナを手当てしようと思った矢先のこの急騰だったので、その前にお前の意見を聞いておきたかったんだ。ありがとう、参考になったよ。また時々、教えてくれよ」
「おう。その代わりここはお前のおごりや、というのは冗談や。まあ、また何かあったら聞いてくれ」
と、秋田は中島の背中を叩いたのだった。